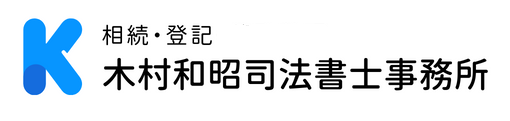遺言書の作成は
大和市の木村司法書士事務所へ
遺言書が無かったために、ご自身の死後に遺産が原因で親族間で争いになることほど悲しいものはありません。遺言書を残しておけば、ご自分の財産をご自分の希望通りに処分することができますし、何よりそこに込めたご自身の思いや考えをご遺族等にお伝えすることができます。
当司法書士事務所では、自筆証書遺言作成サポートと公正証書遺言作成サポートの2つの遺言書作成プランをご用意して、皆様が遺言書を作成するお手伝いをさせていただいております。
この2つのサポートプランのいずれをお選びいただいても、当事務所がじっくりとお客様のお話をお伺いして、将来においてご希望どおりの遺産承継が実現できる遺言書が完成するまで、しっかりとサポートさせていただきます。
遺言書作成なら、大和市の木村司法書士事務所にぜひおまかせください。
遺言書を作成した方が良い場合
- 子供がいないご夫婦で、妻(夫)に全財産を相続させたい。
- 同居の子に自宅を相続させたい。
- 家業の承継者に事業用の資産を相続させたい。
- 法定相続人ではない孫に財産を渡したい。
- 内縁の夫(妻)に遺産を渡したい。
- 相続人はいないが、世話をしてくれた人に遺産を渡したい。
- 自分の死後に相続人同士が遺産分割協議で争わないようにしたい。
当司法書士事務所における遺言書作成サポートの特徴
1. 自筆証書遺言作成サポート
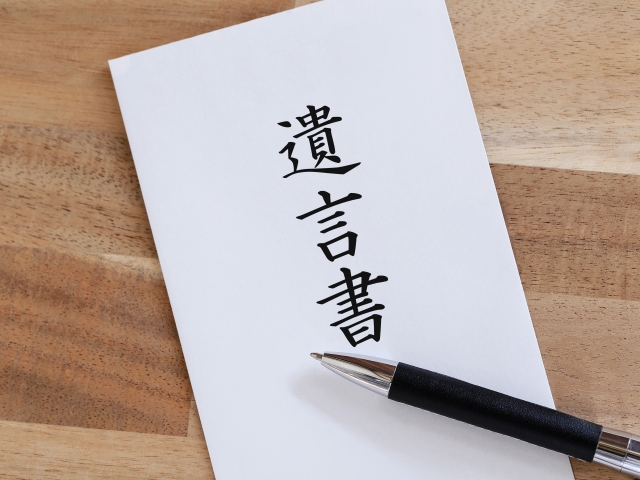
自筆証書遺言の作成をサポートさせていただくプランです。
自筆証書遺言は、目録等を除いた全文を遺言者ご本人が手書きしなければなりませんので、このプランでは、遺言書自体はお客様が書いていただくことになります。
サポートの内容は、当事務所が遺言書の文案を作成し、お客様にはそれを元に実際に遺言書を書いていただき、当事務所は遺言書が完成するまでその添削をさせていただくというものになります。
公正証書遺言とは異なり公証人の手数料がかかりませんので、なるべく費用をかけたくない方にはおすすめのプランです。
また、自筆証書遺言の場合は、相続発生後に家庭裁判所の検認が必要ですが、法務局での自筆証書遺言書保管制度を利用した場合は検認は不要となります。
当事務所は、その手続きの法務局への申請をサポートするプランも別途ご用意しております。
2.公正証書遺言作成サポート
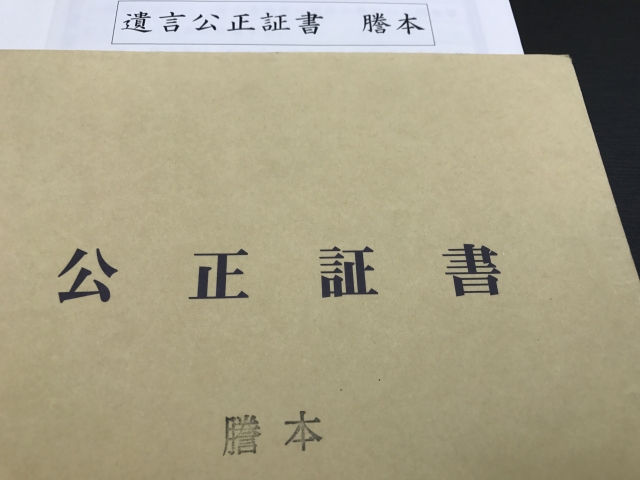
公正証書遺言の作成をサポートさせていただくプランです。
当事務所が、遺言書文案の作成、公証人との打ち合わせ、遺言当日の公証人役場での立ち合いと、公正証書遺言が完成するまで全行程をサポートさせていただきます。
このプランは、遺言書の原文は公証人が作成しますので、遺言書を自筆することが難しい方はこちらのプランとなります。
また、公正証書遺言は、自筆証書遺言とは異なり、相続発生後に家庭裁判所での検認は不要ですので、遺言執行者や相続人に労力をかけたくないという方にもおすすめのプランです。
3.どちらのプランでも土日のご相談が可能です。

当事務所は、事前にご予約いただければ、土日でもご相談が可能です。
平日はお仕事などでお忙しいという方でも、曜日を気にすることなくご依頼いただけます。また、ご相談やお問合せは、電話やメールでも承っておりますので、お時間のある時にお気軽にご利用ください。
遺言書作成サポートプランの流れ
当事務所における遺言書作成サポートプランの流れは以下の通りです。
遺言書作成サポートプランへのお問合せ・ご依頼

遺言書作成サポートへのお問合せは、お電話、メール(相談フォーム)、来所(事前予約制)にて承ります。
遺言書作成サポートのご依頼をご希望の方は、お電話にて来所日時をご予約下さい。
ご来所
当事務所が遺言書文案の作成・公証人との打ち合わせ

お客様から必要書類をお預かりし、当司法書士事務所にて遺言書の文案を作成させていただきます。
公正証書遺言作成サポートの場合は、当事務所が公証人と事前に打ち合わせをし、遺言書原案と公証人手数料の提示を受け、遺言のために公証役場へ行く日時を決定いたします。
遺言書の作成
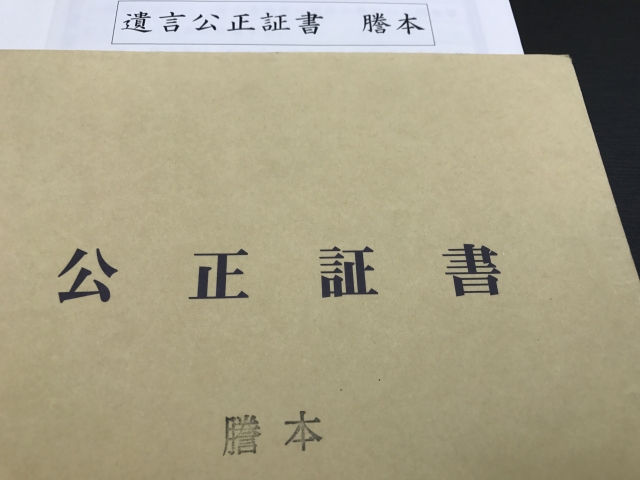
自筆証書遺言作成サポートの場合は、遺言者ご本人であるお客さまに、当事務所が作成した遺言書文案を参照しながら直筆で遺言書を書いていただきます。
当事務所は、正しい遺言書が完成するまでお客様の書かれた遺言書を添削させていただきます。
遺言書が完成したら、法務局での「自筆証書遺言書保管制度」を利用されない場合は、遺言書を封筒に入れて封印して業務終了となります。
公正証書遺言作成サポートの場合は、司法書士、遺言者、証人が予約日時に公証人役場へ行きます。
公証人が遺言内容を遺言者に確認した後、公証人が作成した遺言書原本に遺言者及び証人が署名捺印し、最後に公証人が認証すると公正証書遺言が完成します。
お客様が公証人より公正証書遺言の正本、謄本を受領したら、業務終了となります。
自筆証書遺言書保管制度の利用

自筆証書遺言作成サポートをご利用の方で、法務局での「自筆証書遺言書保管制度」を利用される場合は、申請書は当事務所で作成いたします。
お客様には、ご自身で法務局へ予約を入れていただき、申請書と必要書類、手数料をご持参の上、予約日時に法務局へ行って遺言書保管の申請をしていただきます。予約方法や必要書類等の詳細につきましても当事務所でしっかりとご案内させていただきます。
遺言書作成サポートプランの費用
報酬
| 種類 | 司法書士報酬 | サポート内容 |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言作成サポート | 44,000円~ | ・遺言に関するアドバイス ・遺言書原案作成 ・遺言書添削 |
| 公正証書遺言作成サポート | 77,000円~ | ・遺言に関するアドバイス ・遺言書原案作成 ・公証人との打合せ ・公証役場での立会い |
※相続人調査、財産調査が必要な場合は、別途費用がかかります。
※ご夫婦で同時に作成する場合は、お二人目の上記報酬は半額となります。
公正証書遺言には、別途下記の公証人の手数料がかかります。
公証人の手数料
| 目的財産の価格 | 手数料(遺言加算を含む) |
|---|---|
| 100万円まで | 16,000円 |
| 200万円まで | 18,000円 |
| 500万円まで | 22,000円 |
| 1,000万円まで | 28,000円 |
| 3,000万円まで | 34,000円 |
| 5,000万円まで | 40,000円 |
| 1億円まで | 54,000円 |
※ 上記は相続人または受遺者1名に財産を与える場合です。その他の場合は、手数料加算があります。
※ 公証人に出張してもらう場合にも手数料加算があります。
※ このほかに、謄本代等の若干の手数料がかかります。
その他報酬
| 種類 | 報酬 |
|---|---|
| 公正証書遺言での証人を当事務所で用意する場合 | 日当:証人1名につき11,000円 |
| 当事務所が遺言執行者となる場合 | 相続財産価格の2%~3%(最低21万円) |
遺言書作成サポートの必要書類
公正証書遺言を作成するためには、打ち合わせのために事前に必要になる書類と、遺言当日に公証人役場に持参するものとがあります。自筆証書遺言を作成する場合も、正確かつ執行可能な遺言書を作成するために、できるだけ公正証書遺言と同じもの(ただし、公証人手数料と証人に関するものは除く)をご用意いただければと思います。
事前に必要な書類
公証人が遺言書を作成するにあたって、事前に必要になる書類です。
| 必要書類 | 取得場所/備考 | |
|---|---|---|
| 1 | 遺言者の印鑑証明書(遺言日前3ケ月以内に発行されたのもの) | 住所地の市町村役場 |
| 2 | 遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本(遺言者のもの、財産をもらう相続人のもの)(遺言日前3ケ月以内に発行されたのもの) | 本籍地の市町村役場 |
| 3 | 受遺者の住民票(遺言日前3ケ月以内に発行されたのもの)(相続人以外のものに遺贈する場合) | 住所地の市町村役場 |
| 4 | 不動産の固定資産税納税通知書または評価証明書(財産に不動産がある場合) | 不動産所在地の市町村役場 |
| 5 | 不動産の登記事項証明書(遺言で不動産を特定する場合) | 法務局 |
| 6 | 不動産以外の財産の内容がわかるもの | 預貯金通帳、証券、証書類のコピーなどの金融機関、支店、金額などがわかるもの。メモ書きでも可。 |
| 7 | 証人2名の確認資料 (注1) | 住所、職業、氏名、生年月日のわかる資料 |
| 8 | 遺言執行者の特定資料(注2) | 住所、職業、氏名、生年月日のわかる資料 |
(注1)公正証書遺言には証人2名が必要です。ただし、推定相続人、受遺者とそれぞれの配偶者、直系血族等の利害関係人や未成年者等はなれません。証人は当事務所でご用意することも可能です。
(注2)遺言執行者には、相続人や受遺者でもなれますので、その場合は特定資料は不要です。
遺言当日に公証人役場に持参するもの
- 遺言者の実印
- 証人2名の認印
- 公証人手数料